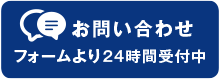親の財産、どう守る?-家族信託という選択-
親が高齢になるにつれ、「財産の管理をどうしたらよいのか」「万一判断力が衰えたらどうしよう」と心配される方も多いのではないでしょうか。厚労省の推計(2022年)によると2050年には日本の65歳以上人口のうち約15%の586万人が認知症になると予想され認知症は誰にとっても“遠い話”ではありません。
認知症になってしまうと物事を判断する能力が衰えるため、不動産を買う・売る、預金を引き出すといったことができなくなります。例えば、「長年一人暮らしをしている父。最近物忘れも増えてきたし、そろそろ施設に入ってもらった方が安心。でも父の自宅を売らないと入所費用がまかなえない。」こんなケースでも、すでにお父様が認知症を発症していると、自宅を売ることも銀行に預けてあるお金をおろすこともできません。
このような問題に備える選択肢のひとつが「家族信託」です。家族信託はその名の通りまだ自分が元気なうちに、財産を信頼できる家族(子供など)に、信託(管理をお願いする)というしくみです。
【メリット】
- 親(委託者)が認知症になっても、家族(受託者)が資産管理を続けられる
- 遺言の代わりとして、亡くなった時にその財産を受け取る人を決めておける
- 成年後見制度より柔軟で、家族が管理者として関与できる
【デメリット】
- 最初の設計が重要かつやや複雑で、専門家のサポートが必要
- 税務署に毎年報告義務があり、財産を任された家族に負担がかかる
- 専門家の手数料や登録免許税などの費用の負担がある
もう一つの選択肢が従来からの「成年後見制度」です。ご家族等にとってどちらが適切なのか、また家族信託との違いなどご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。
【文責:佐野麻衣/プロフィールはこちら】