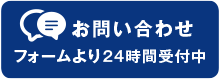ケアマネの「シャドーワーク」問題とその対策
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、要介護者のケアプラン作成やサービス提供事業者との調整を担う専門職である。しかし近年、ケアマネが本来の業務外である「シャドーワーク」に多く対応している実態が明らかになり、深刻な問題となっている。
LIFULL介護の調査によると、「見守り訪問」「休日を問わない電話対応」「通院の付き添い」など、本来の業務ではない内容を依頼しているケースも多数確認された。こうした背景には、多くの利用者が「なんでも相談できる人」と誤解しており、その業務範囲を正しく理解していないことがある。
一方で、ケアマネ自身も「他に頼れる人がいない」「困っているから断れない」といった理由から、業務外の対応を受け入れてしまうケースが少なくない。結果として過重労働が常態化しているのが現状だ。制度改定で担当件数が増える中で、無償のシャドーワークまで担うことは、ケアマネの負担をさらに重くしている。このままでは、ケアマネの離職が進むとともに、新たな人材の確保も難しくなり、制度そのものの持続性が危ぶまれる。
こうした状況を改善するには、まず契約時に業務範囲を明確に伝えることが重要である。加えて、業務外の相談については他の支援機関や介護保険外サービスなど、代替手段を紹介する工夫も必要だ。ケアマネ自身が日々の業務を整理・可視化し、どこまでが本来業務かを、事業所内で共有することも、負担軽減の一助になる。
さらに、ケアマネが対応しがちな生活支援や通院付き添いといった業務には、便利屋的な民間サービスや無償・有償のボランティアの活用も効果的とされる。一部の地域では、信頼できる外部サービスと連携し、ケアマネがコーディネーターとして機能することで、適切な分業が図られている。
ケアマネの本来業務に集中できる環境を整えるには、利用者側の正しい理解の促進、制度・職場環境の整備、地域の支援体制との連携が欠かせない。ケアマネが疲弊せず、持続可能な支援ができるよう、事業所全体での意識と仕組みの見直しが求められている。
【文責 竹内 光彦/プロフィールはこちら】