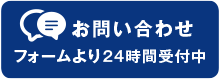長期利益と労働市場
唐突であるが「長期利益」は企業経営の最重要指針、すなわち一丁目一番地である。
短期的であれば、従業員を泣かせて儲ける、お客様をだまして儲ける、銀行や仕入れ先に嘘をついて儲けることも可能である。でもこんな経営が続かないことは誰の目にも明らかである。
逆に長期利益がでているということは、お客様に対して独自の価値を提供し、その支持を受けているということであるし、きちんと儲かり続ける商売をしているからこそ、雇用が守れて給料が払えると言うことである。そして銀行や仕入れ先に対しても対等で誠実な条件での取引が可能ということだ。
企業が評価される場としては、まず金融市場が思い浮かぶ。銀行は常に企業の信用力をスコアリングし、優良企業とそうでない企業を日常的に選別している。そのため経営者は銀行を意識しないわけにはいかない。また製品やサービスの競争市場においても、当然お客様からの厳しい評価にさらされる。銀行のような数的スコアリングはなくとも、買わないという直接行動によって、はっきりと評価される。過当競争になりがちな日本では、以前から競争市場からのプレッシャーは強く働いていた。
そしてここへ来て人不足という課題がいよいよ経営の最前線に浮上してきた。日本でも経営者が労働者からの評価を強く意識しないといけない時代が本格的に始まった。例えば「働き方改革」。理不尽な職場をなくしてもっと働きやすい環境をつくることで生産性を上げるという理念も10年前まではただのかけ声として受け流していた経営者も多かった。恥ずかしながら筆者も少々格好つけで言っていた部分も否定しない。しかし今は違う。働きたくなる職場でないと働き手が来てくれない。働き方改革も本気で取り組まないと、生き残ることすらむずかしいのである。
つまり労働市場から評価をされない企業は淘汰される時代になったということだ。働き手が集まらない企業は持続的に儲けることができない。労働者を真剣に意識して長期利益が初めて成立するのである。
(参考文献:戦略と経営についての論考 楠木建著 日本経済新聞出版)
【文責 飯沼 新吾/プロフィールはこちら】