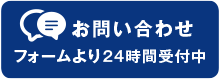相続と事業承継―基本に立ち返って考える
筆者は若いころ、つまりバブル期に東京の税理士事務所で相続税対策の仕事を多く手がけていた。当時はまだ 20 代で、結婚もしておらず、相続の本質どころか、年を重ねることの意味すらよく分かっていなかった。会社経営の経験もない自分が、勢いだけでどれほど危ういアドバイスをしていたかと思うと、今でもヒヤリとする。税理士試験に合格したことで「分かったつもり」になっていた自惚れを、今となっては恥ずかしく思う。
あれから 30 年以上が過ぎ、世の中は再びインフレの時代に入った。タンス預金の価値は年々目減りし、松本地区でも土地の値段がじわじわと上昇している。軽井沢や白馬のように大きく値を上げている地域もあり、東京では中古マンションでさえ 1 億円と聞いて驚かされる。あのころのバブルを思い起こさせるような雰囲気が、今また感じられる。
だからこそ、こんな時代には基本に立ち返りたい。相続で大切なのは、第一「遺産分割(もめないこと)」、第二に「相続税の納税(払えること)」、そして第三に「相続税の節税」である。しかし、実際にはこの順番を逆に考えてしまう人がとても多い。節税策の多くは現金や借入を動かして財産を複雑にし、その結果、遺産分割を難しくしてしまう。経営を顧みず、節税だけを目的に購入した不動産が「負」動産となってしまうケースも少なくない。節税策そのものが悪いわけではない。ただ、歳を重ね、経験を積んだ今だからこそ、その善し悪しを冷静に見極め、人に伝えられるようになったと思う。
事業承継もまた、同じように難しい。創業者が百人に一人の逸材だとすれば、後継者はその残り九十九人の凡人である可能性が高い。株を引き継いで相続税を減らすことよりも、事業そのものをどう引き継ぎ、そして今の時代に合わせてどう再構築するかが何より大切だ。真剣に取り組めば、凡人の二代目でも何とかなる。凡人二代目の私自身が言うのだから、これは間違いない。事業を再び軌道に乗せることができれば、多少株価が高くても十分にやっていけるのである。
【文責:飯沼新吾/プロフィールはこちら】